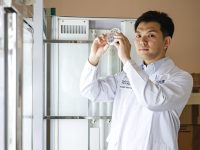※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです
19世紀半ばは、一般にロシア小説の黄金時代と呼ばれる。ドストエフスキーやトルストイ、ツルゲーネフなど、無数の才能がこの時代に一斉に開花した。この時代のロシア文学史を鋭く問い直すと同時に、翻訳家としても活躍している大学院人文科学研究院の高橋知之助教に話を伺った。
ロシア文学研究の道へ

――先生はどんなきっかけでロシア文学を研究する道に入られたのですか。
小学生のころから物語や詩歌が好きで、子ども向けに訳された海外文学や日本文学の本をよく読んでいました。偉人伝や伝記も好きだったので、歴史にも興味がありました。大学に入学したあと日本史学を志望していた時期もありましたが、文学の授業がとてもおもしろくて、ロシア文学を研究することにしたんです。
――英文学やフランス文学、国文学などもあるなかで、ロシア文学を選んだのはどうしてですか。
高校2年生のときに、ロシアの作家トルストイの『戦争と平和』を読んだことがきっかけで、大学の第二外国語としてロシア語を選択しました。だから語学的な理由が大きかったことはたしかです。ただ、今から振り返ると、ロシア文学を選んだことにそれほど必然性があったわけではありません。文学への関心が常に先行してあって、ロシア文学はその入り口くらいに考えています。実際、いまも普段はロシア文学に限らず、いろんな作品を読んでいますから。
「反省」の視点からロシア文学史を更新する

――ロシア文学に関して、どういう研究をなさっているのですか。
私の専門は1840年代から60年代のロシア文学なのですが、その時期の作品を読んでいると、「反省」という言葉にしばしば出くわします。ここでいう反省は、単なる内省とは違います。当時のロシア社会は、西欧の思想や文化が入ってきたことで、ロシアでもヨーロッパでもない、どっちつかずの状態に置かれることになりました。そのなかで知識人たちは、模範とする西欧近代とロシアの現実との間で苦悩し、引き裂かれていきます。そうした分裂を意識する自己意識のあり方、それが反省です。19世紀ロシア文学の根幹には、「反省をいかに乗り越えるか」という希求があります。
この反省という問題を中心に据えて当時のロシア文学を再読していくと、従来の図式的なロシア文学史の見方を少し変えることができるのではないか。そういう問題意識から研究を進めていきました。
――図式的なロシア文学史の見方というのは?
1840年代は「驚くべき十年間」と呼ばれる時代ですが、「ロマン主義からリアリズムへの転換」「西欧派とスラヴ派*の対立」といった図式で理解され、個々の作家・作品もそうした構図のもとに配置されてきました。このような整理は今もなお有効ですが、研究対象に偏りを生じさせてきたことも事実です。
私の基本的な姿勢は、従来の構図からこぼれ落ちてきた作家を掬いとり、その意義を明らかにすることによって文学史を捉え直していく、というものです。具体的には、詩人プレシチェーエフと、詩人・批評家・小説家のアポロン・グリゴーリエフに着目しました。いずれもこれまであまり研究されてこなかった作家ですが、「反省をいかに乗り越えるか」という問いに対して、それぞれに特異なアプローチを示しています。
*19世紀ロシアで発展した思想運動およびそれに属する人々のこと。西欧的な近代化を目指す「西欧派」と対立し、ロシアの伝統を重視する立場をとった。

一例をあげるならば、プレシチェーエフは詩作を通じてそれまでには見られなかったタイプの主人公を創造しています。ロシア詩には「預言者」を主題とする詩の伝統がありますが、プレシチェーエフはその伝統を踏まえたうえで、「反省を乗り越えた先にある」預言者像を新たに提示しました。私はこの新たなタイプの預言者に「小さな預言者」という名を与えました。「小さな預言者」という概念は、ロシア文学における主人公の系譜をたどるうえで、従来の文学史の空隙を埋める重要なピースだと考えています。

『ロシア近代文学の青春――反省と直接性のあいだで 』
プレシチェーエフ、グリゴーリエフといった作家に焦点を合わせ、1840年代のロシア文学史・思想史の読み換えを試みた。
――最近はロシア文学と日本文学との比較研究をされていますね。
はい。日本語の文学を(翻訳を含め)読んできたからこそロシア文学に対して提起できる知見があり、逆にロシア文学を研究しているからこそ日本文学に対して提起できる知見があるはずです。日本語を母語とするロシア文学研究者としてのオリジナリティは、そこに求められるのだろうと思っています。
具体的には、いまお話したロシア文学の「反省」という概念と、日本文学に見られる面白いテーマである「偶然」という概念を軸にして、双方の文学を対話させるような研究を進めていきたいですね。
ふさわしい言葉を模索する、翻訳の楽しみ

――先生はロシア文学の翻訳もコンスタントに手掛けられていますね。
翻訳は楽しいですね。目の前のロシア語のテキストをどうやって日本語にするかを考えることが面白いんです。
翻訳をするようになって、何か使える表現はないかと探しながら小説を読むことも増えました。それは翻訳を始めてから得た、小説の新しい楽しみ方です。日本語の小説を読むときも「この表現、あそこで使えるんじゃないか」とか、「このフレーズはまだ使ったことがないな」といったことを考えながら読むようになりました。
――最新*の翻訳本『19世紀ロシア奇譚集』についてお聞かせください。
これは19世紀ロシアの奇妙な小説を7篇選んで訳したものです。そのうち6篇は本邦初訳です。
この編訳書も、私の研究と関わりがあります。先ほど説明したように、19世紀のロシア文学史には、ロマン主義からリアリズムへという図式的な見方がありますが、ここではそうした図式では見過ごされてしまう面白い作品を、怪奇幻想という大枠のもとに選びました。

ロシア文学には、「スカース」という独特の語りの手法があります。小説は文字の羅列で成り立っていますが、元々は語り、つまり声で語られ、声で聞かれるものが物語の本質です。その「肉声」をどれだけ文字で再現できるか、という指向が強いものをスカースと呼んでいます。この「肉声度」の強い小説は、ヨーロッパや日本にもあると思いますが、特定の名前は日本語や英語にはありません。でもロシアではそれを「スカース」と呼び、文学的な伝統を築いているんです。
今回の翻訳でも、スカース的なところが特に難しかったです。肉声度の強い語りやセリフをどうやって日本語で再現するか。そこに大変、苦心しました。
日本にも落語などの語りの文化があり、それを文字に起こしたものもあります。ですので、落語を聞くなどして、日本におけるスカース的なものは何だろうと考えたりしました。現代小説では、浅田次郎の『壬生義士伝』がまさにスカース的なんです。幕末の南部弁という、私たちには馴染みのない方言が、本当に聞こえてくるかのように書かれています。そういった作品を参考にしながら、翻訳にふさわしい言葉を探していきました。
「読みの技術」を継いでいく、文学研究の役割

――文学研究の醍醐味はどういうところにありますか。
それは私もよく考えるところで、どう伝えたらいいか悩むところです。一つ言えるのは、私たちが海外文学を読めるのは、そもそも翻訳があるからです。その翻訳は研究の蓄積を前提にしています。特に時代が離れてしまうと、社会風俗や言葉の意味も変わってしまいますよね。そういった断絶や距離を埋めるのが研究です。研究によって翻訳が可能になり、私たちは翻訳を通じて作品を楽しめるわけです。
日本文学も同じです。『源氏物語』を現代の私たちが読めるのも、誰かが精読し、読み方を伝えてきてくれたからです。そういう「読みの技術」を継いでいくことが、文学研究の大事な役割なのだと思います。
もう一つ、文学研究の仕事というのは「歴史を作ること」にあります。過去の事象は、語られなければ歴史にはなりません。歴史は語られてはじめて歴史になる(もちろん学術的な手続きを経たうえでの話です)。歴史が必要ないと思う人はあまりいないでしょうし、人間には過去を整理して学びたいという欲求があります。文学研究とは文学に関わる歴史を作ることでもあるわけです。歴史は固定されたものではなく、常に更新されていかなければなりません。だからこそ文学研究も、絶えず続けていく価値があるのです。

インタビュー / 執筆

斎藤 哲也 / Tetsuya SAITO
人文ライター。東京大学文学部哲学科卒業後、大手通信添削会社を経て2002年に独立。
人文思想系を中心に、ライター・編集者として多くの書籍や記事を手がける。
「またこの人に頼みたい」と思ってもらえるような取材・執筆を心がけている。
撮影

関 健作 / Kensaku SEKI
千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。
日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。
「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。