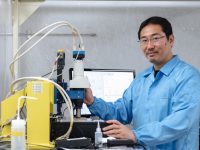※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです
留学で自分の研究がかたちづくられた
もともと留学志向がなかった私でしたが、指導いただいていた先生に「博士号を取ったら海外に修行しに行くものだよ」と言われ、「そんなものなのかな」と思いつつ留学することにしました。
この留学が、私に大きな転機をもたらしました。大学院時代までは研究の範囲も狭くスキルも限られていましたが、ポスドクとして留学したことによって、大学院時代の研究を基盤としながらも、これまでと異なる視点で研究対象を見るようになり、研究の幅がぐんと広がりました。
その結果、現在の研究の土台となる「Adaptation(順応・適応)」という観点にたどり着くことができました。大学院時代から、実際の空間の中で人がどのように視覚を働かせるかという「見え」を研究テーマにしてきたのですが、その「見え」を追求するためには、人がその場の環境に適応しながら視覚を働かせていることをもっと考慮しなければいけないという考えに行き着いたのです。
この気づきをきっかけに、自分のやりたいことの核心がかたちづくられました。
人づきあいが苦手だった自分がガラリと変わる
国際性の大切さも留学で学びました。先ほども述べましたが、自分が留学することになるとはまったく考えていなかった私でしたから、海外での暮らしはカルチャーショックの連続でした。英語も全然分からず、誰かに話しかけられては「何言っているんだろう、どうすればいいのだろう」と右往左往するような状態でした。
それが滞在期間が長くなるにつれて同僚と問題なくコミュニケーションを取れるようになり、親しい友人もできました。そうなると、さまざまな国からやってきた研究者たちとの交流が、がぜん楽しくなりました。
現在、各国の色覚研究者との国際交流活動を続けているのも、このときの交流があったからにほかなりません。そう考えると、貴重な経験をしたと思います。研究のことだけを言えば、日本国内でも充分に成果を得ることはできます。しかし、海外に留学して、現地で生活しながら研究に勤しむことには、それ以上の意味があると私は思います。

偶然によって大きく変わるのが研究の面白さ
帰国後、私は千葉大学に助手として採用していただき、矢口博久教授が進めていた顔の明るさや肌に対する見えの共同研究に参加しました。そこで顔を見るときに特有の視覚に関心を持つようになったことが現在の研究につながっています。振り返ると、それぞれの場所で異なる研究テーマに取り組んできましたが、それらが自分の中で驚くほど自然につながり、うまく融合して現在の研究にいたっている気がします。
その後もさまざまな体験と出会いによって、自分でも思っていなかったテーマに取り組みはじめるなど、転機がたくさんありました。新たな出会いがあるたび、研究は広がります。ときには、それまでまったく考えていなかったことが、突如として自分の研究にとって重要なテーマになることもあります。予測が不可能なのも研究の面白いところ。そう考えて、研究生活を楽しんでいます。