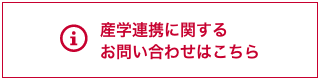※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです
新たな情報通信技術が次々に生まれ、それにともなって犯罪の姿も変化する現代社会。サイバー空間で起きる犯罪に、刑法は後手の対応を迫られることも多い。刑法学者である大学院社会科学研究院の西貝吉晃教授は、他分野の知見をとりいれながら新たな刑法のあり方を模索し、社会に提案している。
「Winny事件」を機に、工学から法律の世界へ

――修士課程まで工学を専攻され、弁護士を経て法学の研究者に。ちょっと珍しいご経歴ですね。
情報理工学系研究科修士2年のとき、後に「Winny(ウィニー)事件」*と呼ばれる事件が発生しました。私が所属していた研究科のパソコン等が警察に押収されているのをテレビで観て衝撃を受けたことを覚えています。
*Winny事件:P2Pファイル共有ソフト「Winny」が著作権侵害に悪用され、2004年5月開発者が著作権法違反幇助の容疑で逮捕・起訴された。裁判では技術開発の自由と著作権保護のバランスが大きな議論を呼んだが、2011年最高裁で無罪が確定した。
――西貝先生が事件に関わっていたんですか?
いえ、同じ研究科の教員の方が「Winny」の開発者だったのですが、Winnyを違法な目的で利用した人たちの共犯者として逮捕されたのです。Winnyは中央のサーバーを介さずにファイルを共有できる画期的なプログラムで、一部の利用者によってゲームなどが大量に共有され、大規模な著作権侵害事件に発展しました。
この事件では違法にファイルをやりとりした人だけでなく、プログラムの開発者まで罪に問われた。「それはおかしいんじゃないか?」と疑問を感じたのが、法律の世界に興味をもったきっかけでした。
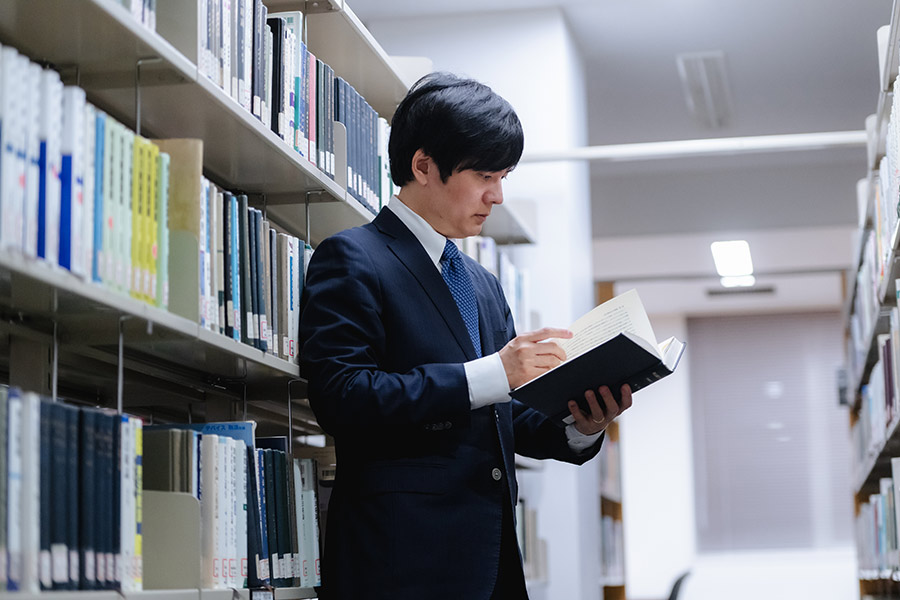
――著作権や特許などの知的財産を扱う法律家になるなら、工学のバックグラウンドも活かせますね。
ところが、ロースクールに進学して学んでいるうちに、Winny事件のポイントは著作権法ではなく、刑法だったとわかってきました。開発者自身は違法なファイル共有をしておらず、違法な共有をした人の「幇助(ほうじょ)犯」、すなわち共犯として逮捕・起訴された。ならばこの件において重要なのは「幇助とは何か」ですが、その定義は著作権法ではなく刑法に書かれているのです。
幇助とは犯罪行為を容易にする行為、または犯罪行為を助長促進する行為だと理解されています。しかしこの短い文言では、まだ、かなり広い解釈の幅があります。だからこそ逮捕・起訴が可能になったとも言えます。
よく引き合いに出されるのは、包丁販売店が売った包丁が殺人に使われたからといってその店が殺人幇助の罪に問われることはない、という議論です。この結論から逆算すれば、犯罪に利用可能なものを開発しただけでは「助長促進」とまではいえないように思われるが、どのような状況があればそういえるのか、さらには本人に助長の意図があったかなどにも目を配らなくてはいけないのではないか。私はそのあたりをきちんと検討したいと思い、ロースクール3年のときに論文を書きました。
物理世界の考え方ではそのまま扱いきれないサイバー空間

――Winny事件では、地方裁判所は幇助であると認めて有罪判決を下しましたよね。
犯罪に使われるものを提供すれば「犯罪を容易にする」にあたるのだと考えれば、そのような帰結になってもおかしくありませんし、実際にはそのような基準が使われてきていたように思います。コンピュータ・プログラムによる犯罪など刑法をつくったときに想定されていなかったとはいえ、既存の幇助の定義を突然修正するのも簡単なことではなかったと思います。
それでも、高裁では地裁とは別の考え方が使われて無罪となり、最高裁*では、さらに高裁とも別の考え方が使われ、開発者には犯罪、ここでは著作権侵害の幇助の故意がなかったということで高裁の無罪の結論が維持されました。
*裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
それまで刑法は、形のあるものを対象として作られてきました。コンピュータ・プログラムによって起こる問題やサイバー空間で起きる犯罪は、物理世界の概念をそのままスライドさせるだけでは扱いきれないことも多々あります。
私の専門はそれを議論し、よりよいあり方を探ることです。この領域を、形のない「情報」を扱う刑法、という意味で、「情報刑法」と呼んでいます。
既存の刑法において、「情報」は扱いに困る存在

――情報通信技術 (information and communication technology: ICT) ※は日々、新しいものが生まれ、それによって社会のあり方さえ変わっていきます。そのようなめまぐるしい変化を追うのは大変ですね。
どうしても、変化し続ける技術や社会に法律がどう対応していくかという研究が多くなりがちですが、私は、変わりゆくものの背後にある“不動の理屈”を発見したいと考えるほうなんです。これを発見し、使っていかないと常に後手に回ってしまいますから。変わらないものを見つけ、それを使って変わりゆく社会について説明し、議論したいと思っています。
*情報技術 (information and communication technology: ICT): コンピュータや通信技術を活用して、情報の収集、処理、保存、共有、活用を行う技術の総称。
――たとえばどういうことですか?
法律の世界では「情報」と「データ」という言葉は同じものとして扱っても特に問題ない、という考え方をする方が結構いらっしゃいます。でも、たとえば企業秘密の入ったデータファイルを(中身の情報は見ることなく)ダウンロードしたときには、情報は得ていないがデータは得ている状態になります。一方で、電話で企業秘密を聞いただけの場合は、情報は得ているけれど、手元にデータは残ってはいない。情報の取得とデータの取得は同義ではないはずです。
ディープ・フェイク*を使った性的画像について、公衆送信だけでなく視聴も罰する法律があるとしましょう。この場合、データをダウンロードしたことによって視聴したと評価されるのか、それとも実際に見て初めて処罰対象になるのか。「情報」と「データ」を区別して考えないと、どんな行為を問題としているかがあいまいになり、立法も解釈も難しくなってしまいます。
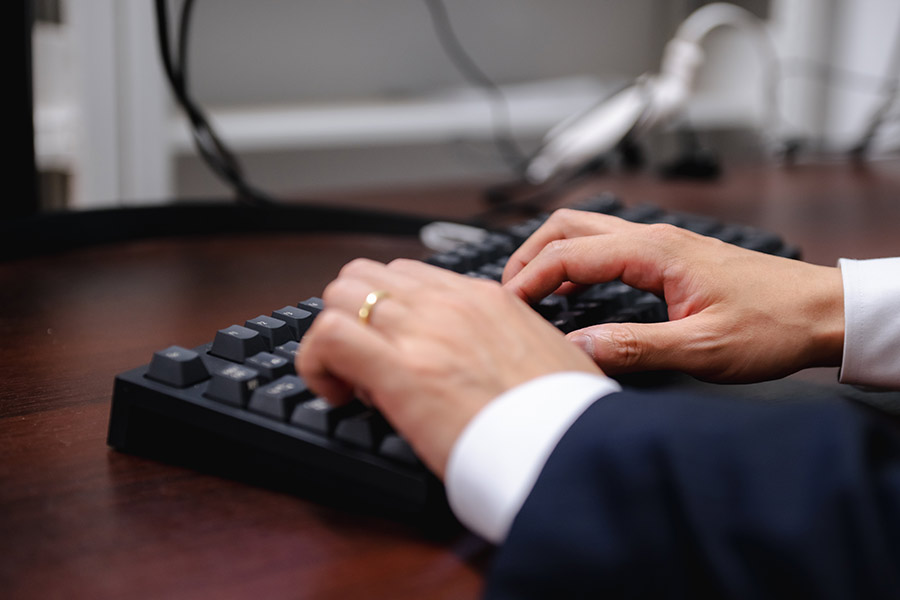
そこで私は、情報そのもの・情報が表現された形式・情報が記録された媒体の3次元で区別して考えるといいのではないか、と提案しています。区別の必要性は法学研究者の間でもわかってもらいにくいのですが、企業秘密の保護を含めたサイバー・セキュリティの領域ではとくに重要なことだと思っています。
*ディープ・フェイク(deepfake): ディープラーニング技術を用いて作成された合成メディア(主に映像や音声)のこと。人物の顔や声を別の人に似せてリアルに加工し、本物そっくりの動画や音声を作る技術。
――Winnyに限らず、新しい情報通信技術はどんどん誕生します。刑法がすべてに対応するのはなかなか難しいのでは?
難しいとはいえ、Winny事件のように、広い範囲の行為に適用できるような解釈が放置されてしまうと、新技術の開発にかかわる人々は、自分がやっていることが違法とみなされるかもしれないと萎縮し、それがイノベーションの芽をつんでしまいます。イノベーションを阻害せず、悪質な事案のみを処罰できるという、バランスの均衡を保つ要を探るのも情報刑法の役目だと思っています。
「この技術は違法に使われる可能性がある」と指摘することは誰でもできます。あるいは、予防的に「悪用や事故の可能性があるからこの技術は規制すべきだ」という議論もよく出てきます。でも、既存の法律の論理を出発点とするのではなく、よりよい社会にするにはどういう法体系や法解釈があるべきなのかを考えていく必要があるでしょう。
たとえばAI(人工知能)については、法律で規制すべきか否かの議論の前に、社会がどうしたいのか、どうなっていくのかを考えることが重要だと思います。AIが人間と同等かそれ以上に精度が高いならよしとするのか、人間以上に「高潔」で、事故発生などの加害の確率がゼロでなくてはだめだと考えるか。強い規制は新しい技術の開発ひいてはその産業の成長、それ自体を諦めることに近いかもしれないことに注意しながら、刑法の在り方を考えるべきだと思っています。
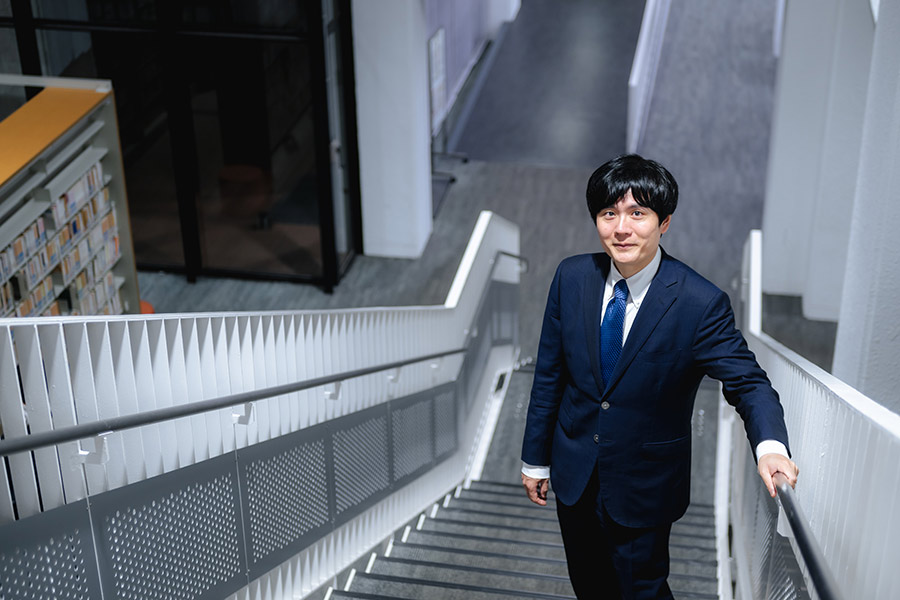
インタビュー / 執筆

江口 絵理 / Eri EGUCHI
出版社で百科事典と書籍の編集に従事した後、2005年よりフリーランスのライターに。
人物インタビューなどの取材記事や、動物・自然に関する児童書を執筆。得意分野は研究者紹介記事。
科学が苦手だった文系出身というバックグラウンドを足がかりとして、サイエンスに縁遠い一般の方も興味を持って読めるような、科学の営みの面白さや研究者の人間的な魅力がにじみ出る記事を目指しています。
撮影

関 健作 / Kensaku SEKI
千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。
日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。
「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。